東山道返り道
2/3ページ目
千次は思った
もう、この村には居られない。役人が来るだろう。権左も手下を連れて、仕返しに来るだろう。母の家を間近に、一目逢いたい気持ちがままならぬ。帰ってはならぬ故郷(ふるさと)の道、二度と帰ってはならない。母に迷惑ばかりかけてしまう。逆戻りになってしまう。
東山道は、仙次にとって逆返りの道だった。「おっか、すまね―、」と、母に詫びながら軒下づたいに、逃げるように村を出た。山裾道から安吉橋に出て、水口の方へ流れて行った。
母「とよ」の家はその後、権左のいやがらせで荒らされた。一人暮らしで目が不自由なため、部屋の隅で身を縮めていた。事が済み、近所の人達が障子をはめてくれた。何度も住まいを変えようかと思ったが仙次が帰って来るのに、居所が解らない様では、との思いから、変えずに此処に住んでいる。
仙次の実の母は、仙次が一才の時、亡くなり、「とよ」によって育てられた。仙次の父は風来(ふうらい)で、仙次が五才の頃には行方が知れなっかた。仙次は十五才の頃、この村を出て以来、一度帰って来たのは二十三才の八月、この武佐宿の賭場で事件が起こった。あれから五年、二十八才になった。
「とよ」は、仙次の実の母「よし」から、仙次をあずかった時の事を思い出し、「よし」に申し訳ないと、自分を責める日々であった。一方、仙次は水口から「土山」の峠に差しかかっていた。野宿は慣れていたが、寝ぐらを何処にしたものかと、夜中に山道を歩いていた。
するとその月明かりの中から、小さな小屋が見えて来た。仙次は小屋の様子をうかがった。人が住んでいる風だったが静まり返っていた。木戸を押して、仙次は、「ご免なすって」と声を掛けたが返事がない。中へ入ってみると、うす暗い中から「だ れ か…」と云う男の声
「ご免なすって、旅の者…、一宿を…」と、仙次は声の者にうかがった。すると、「よ け れ ば…」と、か細い、しわがれた声が聞きとれた。小屋の主(あるじ)は、別に怖がる風でもなかった。
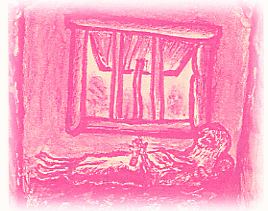
入口から其の方に入ると、小屋の主は、横たわっていた。窓際から射す月明かりの中、青白くその姿が浮かんで見える。病人の様である。人里離れ、藁小屋に身を隠す様に住む者とは、一体…?
仙次には雨をしのぐ寝場所さえあればよかった。しかし…主は病人と云うより、臨終をむかえようとしているかの様であった。節だらけの細い腕や指から、無理な暮らしと淋しさに耐えてきたかの感じであった。
仙次がのぞき込むと、ひげのある顔の中に、遠くはるか彼方を見つめる様な目があった。そうして満身の力で差し出された。手の中に黒ずんだ布袋があった。「こ れ を…武佐村の…」と云ったが、後の声が続かなかった。仙次は、「しっかりなせぇ!」と咄嵯に声を掛けずにいられなかった。又、その先が聞きたかった。主は黙っていた。
静寂が少し流れた―。息は切れていないが、かすかに息はしている。仙次は、小屋の外へ出て、杓で水を汲んで枕元へ戻った。その傍にある布地に水を浸ませて、口元へ持ってゆくとかすかに吸い出した。
「末期の水か…」気になるのは「武佐村の…」と云いかけた言葉である。歳の頃五、六十才くらいだろうか、歳のわりに老けている様でもある。老人と云った感じがする。仙次は、「何か云いたい事は―」と聞くが、口がモグ、モグ動くだけで、何を云おうとしているのかわからない。手渡されたものをよく見ると、何処かの「肌守り」の様である。何処のものか黒ずんでわからないが、「合わせ結び」から表裏はわかる。